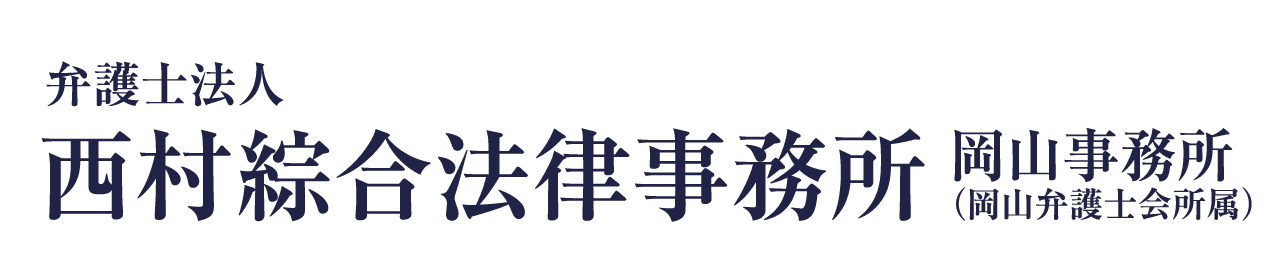交通事故で死亡してしまった場合の損害賠償・逸失利益について解説【弁護士執筆】
交通事故はある日突然発生するものであります。場合によっては皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われてお亡くなりになられてしまうケースもあり、被害者のご家族やご友人の方の悲しみは計り知れないものがあります。
しかし被害者はお亡くなりになられているので、被害者が被った損害は、被害者の遺族が代わりとなって請求するしかありません。
被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つの損害賠償になります。
目次
死亡事故の損害賠償の4分類
|
分類 |
項目 |
|
|---|---|---|
|
A |
死亡するまでの怪我による損害 | 救助捜索費、治療関係費、休業損害など |
|
B |
葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
|
C |
逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
|
D |
慰謝料 | 被害者および遺族に対する慰謝料 |
葬儀費
葬儀費は葬儀そのものにかかった費用に加え、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もあります。
葬儀費には上限があり、自賠責保険では60万円までとされていますが、弁護士会の基準では130万円~170万円程度が適切とされています。また、香典返しなどの費用は葬儀費には認められていませんので注意が必要です。
逸失利益
死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が交通事故によって、得られなくなった将来得られたであろう収入の推計のことです。
例えば30歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り37年間で得られたであろう収入の推計が逸失利益となります。
死亡事故による逸失利益の計算方法は、次の通りです。
逸失利益 = 年収 × (1-生活控除率) × (就労可能年数に対するライプニッツ係数)
①死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。
1.給与所得者:
原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)
2.事業所得者:
原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分
3.家事従事者:
原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金
4.幼児・学生など:
原則として、男子は男性労働者の全年齢平均賃金。年少女性は、全労働者の全年齢平均賃金。その他の女性労働者の全年齢平均賃金。
5.無職者:
原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)
②生活費の控除率
死亡により生活費がかからなくなるための控除。
・一家の支柱:30~40%を収入額より控除
・女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除
③就労可能年数に対するライプニッツ係数
原則として67歳までを就労可能年数としますが、開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
また、平成11年11月の判例により特段の事情がない限り年5%の割合によるライプニッツ方式を採用するようになりました。損害賠償金を一時払いで受け取ると利殖をして利息を得ることができるため不公平な問題がありましたが、現在ではライプニッツ係数を利用して利息の獲得の補正が行われるようになっています。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。
1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目は遺族の慰謝料です。
慰謝料の場合も葬儀費同様に自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、十分確認しておくことが必要です。
弁護士会の基準の慰謝料
|
ケース |
慰謝料金額 |
|---|---|
| 一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 |
| 一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 |
| その他の場合 | 2,000~2,400万円 |
自賠責保険の基準の慰謝料
|
対象 |
ケース |
慰謝料金額 |
|---|---|---|
|
被害者本人 |
– |
350万円 |
|
被害者の父母、配偶者、子供 |
遺族が1名の場合 | 550万円 |
|
被害者の父母、配偶者、子供 |
遺族が2名の場合 | 650万円 |
|
被害者の父母、配偶者、子供 |
遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)
|
ケース |
慰謝料金額 |
|---|---|
| 一家の支柱であった場合- | 1,450万円 |
| 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) | 1,000万円 |
| 18歳未満(有職者を除く) | 1,200万円 |
| 上記以外(妻・独身男女) | 1,300万円 |
※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。
当事務所の解決事例 示談金を350万円増やし、合計2350万円を受け取った事案
被害者の方は道路を歩行中,加害者運転車両に衝突され,亡くなりました。被害者ご遺族は,保険会社から示談金額の提示を受けましたが,示談金額の妥当性に疑問が生じたため,当事務所に相談依頼することになりました。
当事務所で,事情を詳細に聴取し,適正な賠償額を算定した上で,保険会社との間で示談金額の交渉をおこないました。
保険会社の最初の提示額は約2000万円でしたが,当事務所が委任を受け交渉をしたところ,約2350万円まで増額することができました。
代表弁護士 西村啓聡の所感
ご遺族の悲しみや悲痛の声に耳を傾け,保険会社とは,主に慰謝料について粘り強く交渉いたしました。
被害者が亡くなられた場合の慰謝料であっても,保険会社は機械的に処理しようとします。こういった場合,弁護士が代理人となり,ご遺族の方の声に耳を傾けたうえで,事案に応じた個別具体的な交渉をすることがなによりも重要です。
当事務所の解決事例 約3ヶ月で早期解決し示談金として3300万円を受け取った事案
被害者の高齢な男性が信号のない大通りの横断歩道を通って横断中,脇見運転をして被害者に気付かなかった加害車両に衝突され,被害者がお亡くなりになった事案です。親族から相談をいただいた時点では未だ加害者側保険会社から示談金の提示はなく,示談金額について最初から当事務所が担当させていただきました。
被害者遺族の加害者に対する処罰感情が大きかったため,具体的な示談金の交渉をする前に,加害者の刑事裁判の被害者参加代理人となり,加害者の刑事手続に被害者が参加できるよう協力しました。遺族の方も,刑事手続きの中で,その心情を裁判官と被告人の前で十分に説明することができました。その後,保険会社と示談金の交渉を行い,訴訟手続きに移行せずに早期に示談をまとめることができました。結局,遺族の方との委任契約から約3か月で示談をすることができました。
被害者の方は,非常に高齢でしたが,最終的には約3300万円で相手方保険会社と和解をすることができました。約3か月という短期間の交渉で,十分な結果を出すことができました。
代表弁護士 西村啓聡の所感
死亡事故である以上お亡くなりになられたご遺族の方々にとってみれば、当然ながらいくら賠償されても納得できないのは当然のことだと思います。そのような状況の中で、私たちとしては、少しでもご本人の無念を晴らし、ご遺族の方々が今後生活していくうえで経済的な不自由さを感じることがないように、最大限の弁護をさせていただきました。今回は、本人慰謝料、遺族慰謝料を含めて合計3300万円という高額な解決金の賠償が認められました。