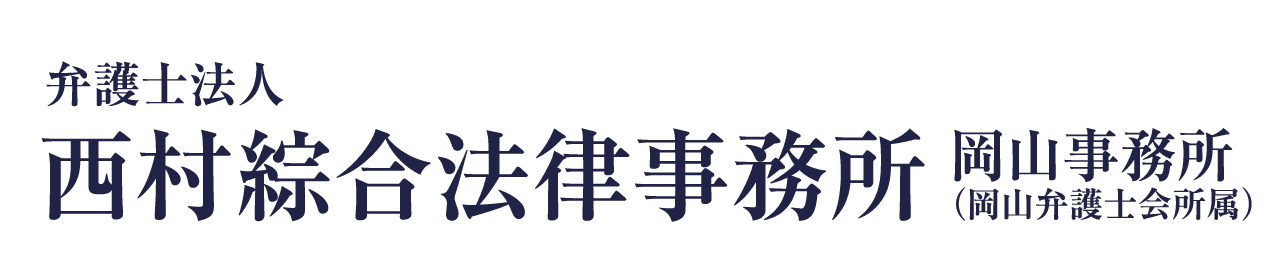ケース別に解説!交通事故被害の症状や後遺症について解説【弁護士執筆】
交通事故に遭ったあと、すぐに症状が出るとは限らず、時間が経ってから痛みや異常を感じることもあります。むちうちやてんかん、肩関節の障害など、被害者によって症状はさまざま。正しく診断を受けずにいると、後遺障害が認められず、十分な補償が受けられないリスクもあります。
本記事では、交通事故により発症することの多い症状や、後遺障害の認定基準・慰謝料の目安などを弁護士が解説。事故直後に何をすべきか、どんな検査や診断が重要かをケース別に紹介します。
むちうち
むちうちとは、交通事故に遭った場合などに、頸椎が不自然にしなってゆがんでしまうため、損傷を受けることです。
むちうちの正式な症状名は、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群、頚部挫傷などとなります。むちうちになると、典型的な症状としては、肩や腕、背中の痛み、しびれなどが発生します。吐き気やめまい、耳鳴りなどの症状をともなうケースもあります。
交通事故が原因でむちうちになった場合には、後遺障害が認定される可能性がありますが、反面、後遺障害が認められずに「非該当」になってしまうケースも多いので、立証方法には注意が必要です。
むちうちで認められる後遺障害の等級
むちうちで認定される可能性のある後遺障害の等級は、12級または14級です。
12級が認定されるのは、レントゲンやMRI画像検査により、異常が認められ、医学的に症状を証明できるケースです。
14級が認定されるのは、上記のような画像検査によっては異常が認められないけれども、症状があることを合理的に推測できるケースです。
12級の認定を受ける方法
12級の認定を受けるためには、画像診断などによってはっきりと症状を証明しなければなりません。そこで、然るべき医療機関で、精度の高い検査機器を使って検査を受けることが必要です。
むちうちの証明のために役立つのは、MRI検査です。医療機関において一般的に利用されているMRI検査機器の精度はかなり幅広く、下は0.5テスラ、上は3.0テスラのものまであります(テスラというのはMRI検査機器の精度の単位です)。
そこで、当初は低い精度のMRI検査機器で検査を受けて異常が発見されなくても、検査をやり直すことによって異常を発見できるケースもあります。
14級の認定を受ける方法
14級の認定を受けるには、症状が合理的に推測されることが必要です。そのためには、交通事故の態様からして症状が発生することが合理的であること、患者の主張が変遷しておらず首尾一貫していること、交通事故がそれなりに重大なものであったことなどが必要です。
また、「神経学的検査」という検査を受けることもお勧めします。神経学的検査とは、医師が患者の首を動かしたり患者の体に刺激を与えたりして反応を見ることにより、症状を推測するための検査です。画像診断によって明確な異常がなくても、患者の主張が合理的で、神経学的検査によっても異常な反応が見て取れる場合、14級が認定される可能性が高くなってきます。
むちうちで認められる後遺障害慰謝料と労働能力喪失率
むちうちになって12級が認定されたら、後遺障害慰謝料は290万円、労働能力喪失率は14%です。14級が認定されたら後遺障害慰謝料は110万円、労働能力喪失率は5%です。
交通事故後、むちうちの症状が出ていたら、弁護士に依頼して確実に後遺障害の認定を受けましょう。
てんかん
てんかんとは、大脳の中の神経細胞が、異常な興奮状態になってしまうことにより、慢性的にけいれんや意識消失などの発作が発生してしまうことです。そして、てんかんの中でも、交通事故などによる外傷を原因として発症するもののことを、外傷性てんかんと言います。
てんかんは、主に以下の3つに分けることができます。
超早期てんかん
外傷を受けてから24時間以内に2回以上てんかん発作が起こった場合です。
早発てんかん
外傷を受けてから1週間以内に2回以上てんかん発作が起こった場合です。
晩発てんかん
外傷を受けてから1週間経過後に2回以上てんかん発作が起こった場合です。
上記のうち「外傷性てんかん」というときには、受傷後8日以降に起こる「晩発てんかん」を意味するのが一般的です。
外傷性てんかんの診断基準
外傷性てんかんの診断をする際には、「walkerの基準」と呼ばれる6つの基準が用いられます。その内容は、以下の通りです。
・現実に、てんかん発作が発生している
・受傷前にはてんかん発作が発生したことがなかった
・他に脳や身体の疾患が見られない
・外傷の程度は、脳が損傷するくらい強度であった
・てんかん発作が最初に発生した時期は、受傷時と比較的近い時期であった
・てんかん型や脳波が脳損傷を受けた箇所と一致している
外傷性てんかんを調べる検査
外傷性てんかんの診断をするための検査は、脳波検査と画像検査です。脳波検査とは、脳波を記録して、てんかん性の放電や異常所見を確認する検査で、画像検査は、MRI検査やCT画像などにとり、脳の損傷状態を調べます。
これらの検査によって異常が検知されると、てんかんがあるとして認められます。
外傷性てんかんで認められる後遺障害
外傷性てんかんによって認められる後遺障害は、以下の通りです。
| 等級 | 内容 |
| 5級2号 | 1月に1回以上てんかん発作があり、その発作の内容が「意識障害のあるなしにかかわらず、転倒を伴う発作」または「意識障害があり、状況に適さない行為をする発作」である場合 |
| 7級4号 | 数ヶ月に1回以上、上記の2種類の発作が起こる場合または、1ヶ月に1回以上、上記の2種類の発作以外の発作が起こる場合 |
|
数か月に1回以上、上記の2種類の発作以外の発作が起こる場合または、薬の服用によっててんかん発作をほぼ完全に抑えている場合 |
|
発作は起こらないけれども、脳波上、明らかにてんかん性棘波がある場合 |
交通事故で外傷性てんかんの後遺障害認定を受けるためには、てんかんと交通事故の因果関係を立証することが重要です。弁護士がサポートしますので、交通事故後にてんかん発作が起こるようになった方は、お早めにご相談下さい。
RSD(カウザルギー)
交通事故に遭うと出血を伴う怪我をする場合があります。この時、人間の体は怪我を少しでも早く治そうし、出血を止めるために血管が収縮をします。通常であれば、この血管は怪我が治れば通常の状態に戻りますが、稀にこの血管が元に戻らない状態になる方もいます。
この状態になると、血管が戻らないことによって血流不足が発生し、怪我をした箇所がズキズキと痛んだり、灼熱痛が起こります。この症状をRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)、CRPSTypeⅠ
(複合性局所疼痛症候群)などと呼びます。
交通事故に遭った後に、このような症状を感じることがあれば、RSDである可能性があります。RSDの等級認定の際、以下の3点がポイントになります。
①関節拘縮
②ズディック骨萎縮
③皮膚色の変化
RSDで後遺障害の等級認定を受けるためには、これら3点の要件を立証しなければ等級認定の獲得は難しいといえます。
この3つの要件について客観的な診断をしてもらうためには、まずはRSDに詳しい専門の医師に診断をしてもらうことが、適切な後遺障害の等級認定を得るために必要です。
当事務所では適正な後遺障害の等級認定獲得のサポートから、適正な賠償金の獲得まで被害者の方に寄り添う形でトータルサポートさせていただきます。RSDでお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
椎骨脳底動脈循環不全(VBI)
椎骨脳底動脈循環不全とは、椎骨脳底動脈という血管の血流が悪化することにより、脳幹や小脳へ充分な血液が送られなくなって、めまいなどの発作が起こる症状です。
椎骨脳底動脈とは、椎骨動脈と脳底動脈のことです。椎骨動脈は、首の左右にある血管であり、椎骨動脈が脳の下部でまとまったものが脳底動脈です。椎骨脳底動脈は、人間の後頭部に血液を運ぶものですから、椎骨脳底動脈循環不全が起こると、後頭部の血液が足りなくなり、症状が起こります。
椎骨脳底動脈循環不全が生じるのは、交通事故によって頸椎を負傷したケースです。頚椎の骨折や脱臼、ヘルニアなどによって椎骨動脈が圧迫されると、この症状につながります。
椎骨脳底動脈循環不全の症状
<主な症状>
めまいー主な症状です。回転性めまいや浮動性めまい、目の前が真っ暗になるめまい発作が発生することもあります。その他は、頭痛・吐き気、嘔吐・眼のかすみ、物が二重に見える・耳鳴り、難聴・平衡感覚の異常・下のもつれ・手足のしびれがあります。めまいを始めとした発作は、首を反らしたときや、首を動かしたりしたときに起こりやすいです。
椎骨脳底動脈循環不全が疑われるときには、神経内科や脳神経外科、耳鼻咽喉科を受診する必要があります。症状はむちうちと似ていますが、受診機関はむちうちと異なり、整形外科ではないので注意しましょう。
椎骨脳底動脈循環不全の治療・検査方法
椎骨脳底動脈循環不全の主な治療方法は、脳循環の代謝を改善する薬や鎮痛消炎薬、抗めまい薬などを使った薬物療法です。頸椎に異常が発生している場合には、手術を行うケースもあります。
症状を明らかにするための検査としてはレントゲン撮影やCT画像、MRI画像などの画像検査を行います。特に、MRI撮影によって血管を撮影するMRA検査が重要です。
それ以外にも、平衡機能検査、聴力検査や自律神経についての問診・血圧テスト、神経学的検査などを行いますし、脳幹や小脳の状態を調べるための、ETTという検査を行うこともあります。
椎骨脳底動脈循環不全で認められる後遺障害の等級
椎骨脳底動脈循環不全となった場合、人によっては完治することもありますが、後遺障害として症状が残るケースもあります。その場合、程度に応じて後遺障害等級が認定されます。認定される可能性のある等級は、3級~14級までと幅広いですが、他の症状と相まって後遺障害認定を受けることが多いです。
椎骨脳底動脈循環不全の症状が残ると、めまい発作などが起こって日常でも悩まされるものです。まずは、耳鼻科や神経内科を受診して、その後、後遺障害認定のためには弁護士に相談されると良いでしょう。
高次脳機能障害
交通事故で頭部を損傷すると、高次脳機能障害になってしまうことがあります。すると、日常生活にもさまざまな支障が発生しますし、仕事ができなくなってしまうこともあり、影響が大きいです。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、脳の認知機能に関する障害です。つまり、脳が持つさまざまな認知や感覚の機能が働かなくなってしまいます。
具体的には、以下のような症状があります。
●記憶障害
記憶力が低下したり、失われたりする
●注意障害
集中できない、ぼーっとする、1つの作業に長時間取り組めない
●遂行機能障害
計画を実行できない、効率よく物事を進められない、複数のことを同時にできない
●失語症
言葉が出ない、出にくい
●失行症
適切な行動ができなくなる(1人で服を着られない、ボタンを留められない、自転車に乗れないなど)
高次脳機能障害の症状が酷くなると、自分で身の回りのことがほとんど何もできなくなり、常に介護を要する状態になることもあります。
高次脳機能障害で認められる後遺障害の等級
交通事故が原因で高次脳機能障害になったとき、後遺障害の認定を受けることができます。認定される可能性がある等級は、以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
| 1級1号
(要介護) |
日常生活に必要な動作もできず、常に介護を要する状態 | 2800万円 |
| 2級1号
(要介護) |
日常生活に必要な動作が限定されており、家族などによる介護が随時必要となる状態 | 2370万円 |
| 3級3号 | 日常生活に必要な動作はできても、仕事をすることは困難な状態 | 1990万円 |
| 5級2号 | 単純な労働はできるが、一般の人と比べると労働能力が著しく限定されている状態 | 1400万円 |
| 7級4号 | 簡単な仕事しかできない状態 | 1000万円 |
| 9級10号 | 一般的な仕事をすることはできても、作業効率や持続的な作業が難しい状態 | 690万円 |
高次脳機能障害になったときの対応方法
高次脳機能障害になっても、忘れっぽくなったとか怒りっぽくなった、協調性がなくなったなどの「性格の変化」だと思われて見過ごされる例が多く、本人にも自覚がないことが多いです。しかし、実際には、重大な脳障害が隠れている可能性があります。
交通事故後、ご本人の様子に変わったところがあれば、すぐに脳神経外科の専門医を受診する必要があります。お困りの際には、弁護士が必要なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談下さい。
肩関節周囲炎とは
肩関節周囲炎とは、40代や50代以降の人を中心にして、肩関節の周囲組織が老化することにより、明確な原因なしに発生する症状です。肩関節が痛み、肩が上がりにくくなるなどの運動障害が発生します。
肩関節周囲炎になると、当初は疼痛が起こりますが、動くと痛むので肩を動かすことができなくなり、動かさなくても痛みが出るようになり、肩関節が固まっていきます。そして、肩関節がほとんど動かなくなると、その後、徐々に痛みが軽くなっていきます。すると、だんだんと固まりが解けてきて、元のように動かせるようになります。このように、肩関節周囲炎は、通常一般では「治る」症状と考えられています。
肩関節周囲炎の治療方法
肩関節周囲炎になった場合、ヒアルロン酸を注入したり、鎮痛剤を服用したりします。痛みがある間は肩を固定して動かせないようにしておき、痛みが軽減してくると、リハビリを行って徐々に元に戻していきます。
肩関節周囲炎が交通事故後遺障害となるケース
ただ、肩関節の痛みや拘縮(固まること)は、交通事故が原因でも起こることがあります。
そして、「肩関節周囲炎」と診断されると、「単なる五十肩」と思われて、交通事故の後遺障害とは受け止められないことが多いです。五十肩の場合には、上記のように治りますから、後遺障害にはなりませんし、交通事故との因果関係もないと考えられるからです。しかし、そのように診断されたケースでも、きちんと調べると、肩に器質的な損傷が見つかって、交通事故との因果関係が明らかになることもあります。実際に、肩関節周囲炎になった事例で、交通事故との因果関係を認め、後遺障害12級を認定した裁判例もあります(高松高裁平成11年2月16日)。
そこで、交通事故後に肩が痛み始めた場合、医師が「肩関節周囲炎」と診断して「交通事故とは無関係な、五十肩です」と言っても、鵜呑みにせず、レントゲン検査や肩関節の造影検査、MRI検査などを受けて病態をしっかりと確認すべきです。当初は画像検査によって異常を発見できなくても、より精度の高いMRI検査を受け直すことにより、病態が確認できるケースもあります。
肩関節周囲炎で認定される後遺障害の等級
肩関節周囲炎が後遺障害として認定される場合、認定される可能性のある等級は、12級か14級であることが多いです。
12級の場合、後遺障害慰謝料は290万円、労働能力喪失率は14%です。
14級の場合、後遺障害慰謝料は110万円、労働能力喪失率は5%となります。
交通事故後、肩関節周囲炎(五十肩)と診断された場合にも、後遺障害が認定される可能性があります。
胸郭出口症候群
胸郭出口症候群とは、「胸郭出口」という部分において、頸椎から腕へと走っている腕神経叢(神経の束)と鎖骨下動脈が、圧迫されたり引っ張られたりして(牽引)、上半身の痛みやしびれを引き起こす症状です。胸郭出口は、一番上の肋骨の部分です。
一般的に、胸郭出口症候群になりやすいのは、男性なら筋肉質の人、女性ならなで肩の人が多いです。そして、交通事故に遭ったときにも、これらの神経や血管は、鎖骨や第一肋骨、筋肉などに圧迫されたり引っ張られたりすることがあるので、胸郭出口症候群になってしまうことがあります。
胸郭出口症候群の症状
胸郭出口症候群の主な症状は、以下のようなものとなります。主な症状は、腕から肩にかけての痛みやしびれです。首や肩のこりが発生することも多く、チアノーゼや冷感、発汗や吐き気、頭痛などが発生することもあります。
胸郭出口症候群の治療方法
胸郭出口症候群になった場合の当初の治療方法は、保存療法です。装具をつけて圧迫や牽引を防いだり、斜角筋ブロックや温熱療法をしたり、ノイロトロピンなどの薬物を投与したりします。
それでも効果がないときには、外科手術を行うこともあります。手術では、神経を圧迫している第一肋骨や頸肋という部分を切除したり、前斜角筋を切除したりして、圧迫や牽引の原因を除去します。
胸郭出口症候群で有効な検査方法
胸郭出口症候群でよく使われているのは、誘発テストと画像診断です。誘発テストは、体の特定の部分に特定の刺激を与え、その反応を見る検査です。
モーレイテスト、アドソンテスト、ライトテスト、エデンテスト、ルーステストの5つがよく利用されます。画像検査としては、レントゲン検査や血管造影検査を利用します。
胸郭出口症候群で認定される後遺障害の等級
胸郭出口症候群で認定されやすい後遺障害の等級は、14級9号ですが、12級13号が認定されることもありますし、9級10号が認定された例もあります。
胸郭出口症候群の難しさ
さまざまな検査手法を使っても、交通事故によって胸郭出口症候群になったことを証明することは簡単ではありません。
そもそも、医師が胸郭出口症候群を見逃してしまうことがあります。また、もともと筋肉質やなで肩などの身体的特徴がある人が、心因的な原因などによって胸郭出口症候群になることがあり、そうした場合には交通事故との因果関係も問題となります。さらに、誘発テストは必ずしも信頼されているとは言えませんし、画像診断については、健常な人でも異常が写ることがあるので、やはり完全な検査方法にはなりません。
このように、胸郭出口症候群で後遺障害として認定されることには困難を伴うことが多いです。確実に認定を受けるためには、交通事故専門弁護士まで、ご相談下さい。
バレリュー症候群
バレリュー症候群とは、首に損傷を受けることにより、頭痛、不眠や倦怠感などの症状が発症するものです。1926年~1928年にかけて、フランス人の「バレ」と「リュー」という人が報告したため、その名をとって、バレリュー症候群と名付けられました。
バレリュー症候群の原因は、頸部が損傷を受けることにより、自律神経や交換神経節に刺激を与えてしまうことです。交通事故によって頸部に衝撃が加わると、バレリュー症候群が発症することがあります。
バレリュー症候群の症状
代表的な症状は、頭痛です。また、不眠も続きます。体の全体的な症状としては、倦怠感や疲労感、局部的な熱感、脱力感、しびれなどがあります。めまい、耳鳴り、難聴や眼精疲労、目の調節障害や流涙障害なども起こります。
肩コリや腰痛、背中の痛みが発生することもありますし、動悸や息切れ、食欲不振や胃もたれ、吐き気や腹痛、下痢、便秘なども発生します。手足の冷えや、頭が重い感覚を受けることもあります。
バレリュー症候群の治療方法
バレリュー症候群の治療方法は、基本的にはむちうちのものと似ていますが、バレリュー症候群特有の治療方法もあります。
具体的には、星状神経節ブロック(星状神経節の周囲に局所麻酔をして交感神経の働きを軽くすることにより、症状を改善する方法)、硬膜外ブロック、トリガーポイントの注射などを行います。これらはすべて、交感神経の働きを一時的に抑制し、人が本来持っている自然治癒力によって、交感神経と副交感神経のバランスをよくするものです。症状の程度が酷く、頸椎が変性してしまっているときには、外科手術が必要になるケースもあります。
バレリュー症候群になった場合の通院先は、麻酔科やペインクリニックです。むちうちと同様、整骨院や接骨院でも症状改善のための施術を行っています。多くのケースでは、治療2ヶ月程度で改善が見込めますが、中にはなかなか症状がおさまらず、いつまでも頭痛や頭重感、めまいなどの症状が続くこともあります。
バレリュー症候群で認定される後遺障害
バレリュー症候群になり、長期にわたって治療をしても改善が見込めない場合には、後遺障害として認定される可能性もあります。多くのケースでは、画像検査をしても、明らかな異常を認めることがなく、認定される後遺障害の等級は、14級9号です。頸椎に変性が発生している場合には、12級12号が認定されます。
バレリュー症候群になった場合、明確な他覚所見がないため後遺障害が否定されることも多いです。
びまん性軸索損傷
びまん性軸索損傷(びまんせいじくさくそんしょう)とは、脳に衝撃が加わることによって、脳の線維組織が広範囲にわたって損傷を受けることです。交通事故に遭って、頭を強く打ったり衝撃が加わったりすると、びまん性軸索損傷になってしまうことがあります。
びまん性というのは、全体に発生する症状のことです。これに対する言葉が局所性です。つまり、脳の一部では済まず、全体が損傷を受けてしまっているということです。軸索とは、神経細胞の突起のうち、最も長いもので、信号を伝達する働きをしています。
びまん性軸索損傷になると、脳内の神経細胞突起が広範囲で損傷を受けるので、脳が正常に機能しなくなってしまいます。
びまん性軸索損傷の症状
交通事故でびまん性軸索損傷となった場合、まずは事故直後に意識を失うことが多いです。
ただ、数時間が経過すると、意識は回復します。その後、脳の認知機能に障害が発生して、高次脳機能障害になってしまう例が非常に多いです。
高次脳機能障害とは、脳の認知機能障害の総称です。具体的な症状としては、忘れっぽくなったり、物事を計画的に行うことができなくなったり、集中力がなくなったり、怒りっぽくなったりすることがあります。酷いケースになると、ボタンを留めるなどの日常的な動作すらできなくなるので、介護を要する状態になることもあります。
びまん性軸索損傷で高次脳機能障害になると、症状の内容や程度によりますが、9級以上の認定を受けることとなります。常時介護が必要な状態になると、要介護の1級が認定されます。
びまん性軸索損傷で後遺障害認定を受ける方法
びまん性軸索損傷になった場合、CT画像によっては異常を見つけられないことが多いです。特に、事故直後に画像を撮影しても、正常な脳とほとんど変わらないので、症状が見過ごされがちです。
有効なのはMRI画像とされており、これであれば、事故直後でも小さな出血を発見できることがあります。そこで、交通事故に遭って頭に衝撃を受けて意識を失った場合には、まずは事故直後に精度の高い機器を用いてMRI検査を受けることが大切です。
また、交通事故後数週間~数ヶ月が経過して慢性状態になってくると、脳全体が萎縮してくることが多いです。すると、びまん性軸索損傷による異常を発見しやすくなります。そのためには、事故直後の画像と後日の画像を比較することが重要となってきます。
びまん性軸索損傷は、事故直後では発見しにくい上、高次脳機能障害の症状が出ても、単なる性格の変化であると見逃されることがあります。交通事故後、頭に衝撃を受けて意識障害を起こしたなら、まずばびまん性軸索損傷を疑い、精密検査を受けるべきです。
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)
脳脊髄液減少症とは、脳や脊髄の膜である硬膜やくも膜が損傷を受けることにより、内部の髄液が外に漏れ出してしまう症状です。
脳と脊髄は、硬膜という膜で覆われており、その中には髄液という液体が入っており、脳の内側の圧力は、常に一定に保たれています。ところが、交通事故によって頭部に損傷を受けると、頭蓋骨の中の硬膜が損傷を受けて、髄液が漏れてしまうのです。そうなると、脳圧が一定に保たれなくなるので、さまざまな症状が発生します。脳脊髄液減少症は、脳圧を減少させるので、低髄液圧症候群とも言われます。
脳脊髄液減少症の症状
脳脊髄液減少症になると、以下のような症状が発生します。
- 立ち上がったときの頭痛・視力低下、聴力低下・首や肩の痛み・めまい、耳鳴り
- 吐き気・倦怠感(疲れやすい)
脳脊髄液減少症の治療方法
脳脊髄液減少症となった場合、交通事故直後の段階では、まずは2週間程度、安静にして十分な水分摂取を行います。点滴をすることもあります。
1ヶ月が経過しても改善しない場合や、安静や水分摂取では良くならない場合には、ブラッドパッチという方法で治療をします。ブラッドパッチとは、髄液が漏れている場所に患者自身の血液を入れて、血液を凝固させることにより、髄液の漏れを止める治療法です。
脳脊髄液減少症と後遺障害認定
脳脊髄液減少症は、最近になって、ようやく認められてきた症例です。つい最近までは、裁判でも、否定的な判断が続いていました。
ただ、平成22年4月、厚生労働省が、脳脊髄液減少症に関する検査に対し保険を適用すべきという見解を示しました。また、平成23年10月14日には、脳脊髄液減少症の画像診断基準とその他の基準も発表しています。このような国の動きを受けて、平成23年からは、裁判所でも脳髄液減少症を認められるようになっています。
認定される等級としては、9級、12級、14級が多いです。
| 等級 | 内容 | 後遺障害慰謝料 | 労働能力喪失率 |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 690万円 | 35% |
| 12級13号 |
|
290万円 | 14% |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 | 5% |
脳脊髄液減少症は、比較的最近になって認知された症状ではありますが、今や厚生労働省による認定基準も明らかにされており、後遺障害として認定を受けられる症状となっています。適切に後遺障害認定を受けるには、弁護士のサポートが必要ですので、あてはまる症状がある方は、是非とも一度ご相談にお越し下さい。