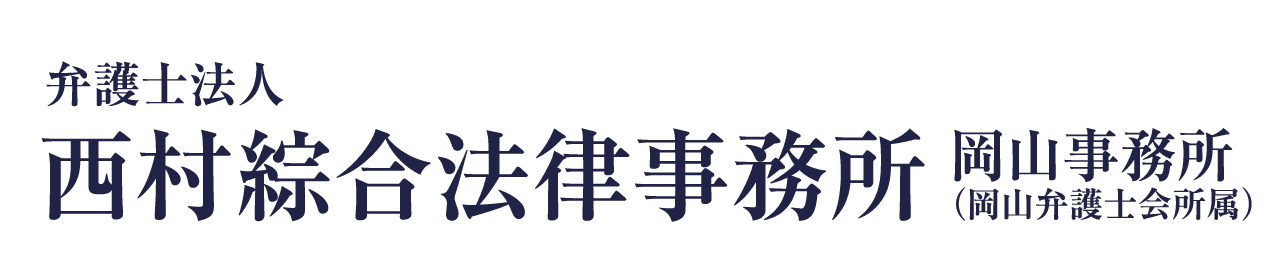脳外傷(遷延性意識障害・高次脳機能障害)に強い弁護士の重要性について
交通事故で脳に外傷を負い、遷延性意識障害や高次脳機能障害になった場合には、専門の弁護士に相談したり、対応を依頼したりする必要性が非常に高いと言えます。
こうした傷病にかかると、後遺障害等級認定手続きを始めとして、多くの法律問題に対応しなければならないからです。遷延性意識障害になると、被害者のご家族は転院先を見つけることにも一苦労されることが多いです。また、将来的に自宅介護とするのか施設介護を選ぶのかによって、とるべき対応方法が全く変わってきますし、賠償金の金額も変わります。
高次脳機能障害となった場合、まずは適切に後遺障害等級認定を獲得することが重要です。
保険会社と争いになることも多いので、適切な医証を用意して、過去の裁判例の考え方に従い、手続きを進めなければなりません。医師に対し、被害者に有利な内容の意見書の作成を求めることも有効です。脳外傷を専門としない弁護士の場合、こういった対応をとることができないので、被害者が本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなったり、本来しなくて良い苦労をしなければならなくなったりします。
遷延性意識障害や高次脳機能障害の専門知識を持ち、こうした被害者の方を専門に取り扱っている弁護士に対応を依頼することにより、困難な事例でも、被害者の方を適切に救済することが可能となります。
目次
遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態になってしまうことです。
交通事故で脳が強く衝撃を受けて、脳の大部分が壊死したり損壊してしまったりすることにより発症します。自力移動や摂食、排泄などができず、他者と意思疎通することもできません。基本的に、一生、全面的な介護が必要な状態となります。
後遺障害の等級としては1級が認定されます。遷延性意識障害になると、ご家族様にはさまざまな困難な問題が降りかかります。
たとえば、自宅介護か施設介護かを決定しなければなりませんし、自宅で介護するとしても、介護士に依頼するのか家族が介護するのかを決めなければなりません。自宅で介護をするなら、自宅改装も必要となります。
遷延性意識障害の定義
- 自力移動ができない。
- 自力摂食ができない。
- 屎尿失禁をしてしまう。
- 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
- 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
- 声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると上限の4,000万円までの補償を受けることができます。遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。
日常介護・住宅改修・将来の介護人件費も賠償対象になる場合があります
遷延性意識障害の状態では、自力での生活ができず、24時間の介護が必要となるため、自宅をバリアフリーに改装したり、介護人を雇ったりする費用が発生します。
これらの費用も、適切に請求すれば賠償対象となる可能性があります。ただし、詳細な見積書や介護実態の記録など、具体的な資料が不可欠です。弁護士と連携しながら、請求のための証拠を早期に整えることが重要です。
転院問題への対処
転院問題とは、遷延性意識障害の患者が入院する施設の問題です。
交通事故後、被害者の方は病院に入院することになりますが、多くの病院では、ずっと入院し続けることが認められません。症状が落ち着いてくると、転院を促されます。その後、新しい病院に移っても、3ヶ月ごとくらいに転院を促され、病院を探し続けなければならない状態になります。このようなことになる理由は、病院では、3ヶ月以上入院すると、保険の点数が下がってしまい、病院の収入が減る制度になっているからです。また、急性期を過ぎると、特段病院における処置が不要になるということもあります。
転院をするときには、脳神経外科の専門医のいる病院を探さねばなりませんし、転院先の病院で、後遺障害認定に必要な検査に対応しているのかを調べなければなりません。また、他の病院での検査結果をもとに、後遺障害慰謝料診断書を始めとする診断書を書いてもらえるのかも問題となります。早期に脳外傷分野に強いの弁護士にご相談を頂いておりましたら、こうした重要なポイントをお伝えして、適切な医療機関を選択いただくことが可能です。
このことによる、将来的に適切に後遺障害認定を受けて、十分な医療を受けることができる環境を整えることにもつながります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、脳の認知機能傷害です。
脳が損傷を受けることにより、各種の認知機能が低下したり失われたりします。症状としては、記憶障害や注意傷害、遂行機能傷害や失語症、失認症などがあります。本人に傷病の自覚がないことも多く、周囲に知識が無い場合、「単なる性格の変化」と思われてしまうことも多いです。
症状の内容や程度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級の後遺障害が認定される可能性があります。高次脳機能障害の場合、適切に後遺障害が認定されにくく、被害者やご家族の方が苦しまれているのに、必要な賠償金の支払いを受けられない例を見ることが多々あります。
高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級1号 (要介護) | 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの |
| 2級1号 (要介護) | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
| 3級3号 | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
| 5級2号 | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
| 7級4号 | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
| 9級10号 | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
医師が診断書に書かなければ、賠償請求が困難にな
高次脳機能障害の賠償を受けるには、医師の診断書や専門的な検査結果が不可欠です。
単なる「記憶障害あり」といった曖昧な記述では、後遺障害認定が通らないケースもあります。弁護士があらかじめ診断の方向性や必要な検査項目を整理したうえで医師に依頼することで、適切な書類の取得が可能になります。
専門医の診察と、弁護士による戦略的準備が必要
脳外傷に詳しい専門医の診断は、後遺障害等級認定において極めて重要です。
また、認定手続では「障害があること」だけでなく、「どれだけ生活や就労に支障をきたしているか」が問われます。これを立証するには、医学的証拠に加え、日常生活や介護状況に関する詳細な情報が必要となり、弁護士の関与が有効です。
後遺障害等級1級・2級の認定に向けた準備・進め方
等級により賠償金が2,000万円以上変わることもある
後遺障害等級は賠償額に直結します。たとえば1級と3級では、逸失利益の算定額が2,000万円以上変わることもあり、適正な等級認定が極めて重要です。
どれほど重大な障害が残っていても、証拠が不十分であれば低い等級にとどまり、必要な賠償を得られないおそれがあります。
「医師任せ」にしない。弁護士が資料作成に関与すべき理由
後遺障害診断書は、医師が書きますが、診断書の形式や内容が不十分なまま提出されてしまうこともあります。
弁護士が事前に検査結果や生活状況の情報を整理し、適切な文言を医師に依頼することで、等級認定に必要な観点が網羅された診断書が得られる可能性が高まります。
家族の介護状況や生活実態も、認定判断に大きく影響する
後遺障害認定では、被害者本人の状態だけでなく、家族がどのように介護を行っているかも重要な判断材料になります。
介護日誌や写真、介護時間の記録などが有効な資料となります。弁護士がどのような資料が必要かを指示することで、提出資料のクオリティが大きく向上します。
弁護士への早期相談が将来を左右します
事故から時間が経ってしまうと、必要な証拠が散逸したり、記憶が曖昧になってしまうことがあります。
適正な賠償金を得るためには、事故直後からの計画的な準備が鍵を握ります。弁護士はその計画をサポートし、必要な証拠を確実に整備していく役割を担います。
保険会社は減額交渉のプロ ─ 個人で対応してはいけない理由
示談金の提示が早すぎるときは“罠”を疑うべき
交通事故の加害者側の保険会社は、できるだけ早期に、低額の示談金で解決しようとする傾向があります。
特に後遺障害の内容がまだ定まっていない段階で、保険会社から「これで示談しませんか」と金額提示があった場合には注意が必要です。後になって症状が重くなっても、示談を結んでしまうと追加請求はできません。感情に流されず、冷静に一度立ち止まって弁護士にご相談ください。
保険会社との交渉は“金額の引き上げ”を前提に行うべき
保険会社から提示される金額は、被害者にとって必ずしも十分な補償とは限りません。裁判例に基づく適正額に比べ、著しく低いことも珍しくありません。
弁護士が交渉に入ることで、医学的根拠や法的根拠をもとに、より高額な賠償金を目指して交渉を行うことが可能になります。個人では見落としがちな項目まで含めて、戦略的に金額の最適化を図ることが重要です。
弁護士に依頼することで賠償金が跳ね上がるケースも
医師に対する意見書依頼、カルテ精査、検査依頼などが可能
弁護士は、医療記録を法的観点から分析し、診断書や意見書に必要なポイントを整理したうえで医師に依頼できます。
特に脳外傷の場合、画像や神経学的検査の記録をどう読み解くか、何を強調するべきかの判断は専門的知識が求められます。適切な医証を整えることで、等級認定や賠償額に大きな差が出ます。
過去の裁判例と照らし合わせて、適切な金額を主張できます
損害賠償額は、過去の裁判例の傾向を踏まえて主張することが非常に効果的です。
弁護士は過去の類似事例を調査し、それに基づいて保険会社と交渉を行うことで、相場以上の金額を目指すことが可能です。被害状況が重く、生活や介護に多大な影響がある場合、過去の事例よりも高額な賠償を勝ち取ることもあり得ます。
交渉の中で“数字を支えるロジック”を立てられるのは弁護士だけ
賠償金額をただ提示するだけでは、保険会社は応じません。「なぜその金額が妥当なのか」「何を根拠に主張しているのか」といった論理構成が不可欠です。
これを法律や医療、介護の知識をもとに組み立て、交渉を行えるのが弁護士の強みです。感情や希望ではなく、事実と根拠に基づいた主張が、保険会社や裁判所を動かす鍵になります。
交通事故でご家族に重たい障がいが残ってしまったら
損害の全額が補償されるとは限りません。毅然とした対応を進めましょう。
現実には、保険会社はあらゆる理由を挙げて賠償額を抑えようとします。
「本当にその金額が必要なのか」「過剰な介護ではないか」といった反論を受けることもあります。必要な賠償を確保するには、感情的な主張ではなく、客観的な証拠と論理に基づいた対応が不可欠です。ご家族の将来を守るためにも、毅然とした交渉が求められます。
後遺障害の等級認定は将来の補償に直結します。慎重に進めましょう。
賠償金の多くは、後遺障害等級によって決まります。
そのため、等級認定の段階でミスや漏れがあると、その後の補償額が大きく変わってしまいます。一度下された認定は、後から覆すことが非常に難しいため、初動から慎重に、戦略的に対応することが大切です。
弁護士が関与することで、後悔のない等級認定手続を進めることができます。
まずは早期の無料相談をご利用ください
交通事故による重度障がいのケースでは、ご家族だけで全てを把握し、対応することは非常に困難です。医療・介護・保険・法律のすべてを横断して適切な対応が必要になります。
当事務所では、岡山に密着した法律事務所として、交通事故後の法的サポートに力を入れています。初回相談は無料で、オンライン面談にも対応していますので、外出が難しい方やご遠方の方もお気軽にご相談いただけます。
経験豊富な弁護士が、ご家族の将来を見据えた戦略的な対応をご提案いたします。適切な補償を受けるために、まずは無料相談をご利用ください。