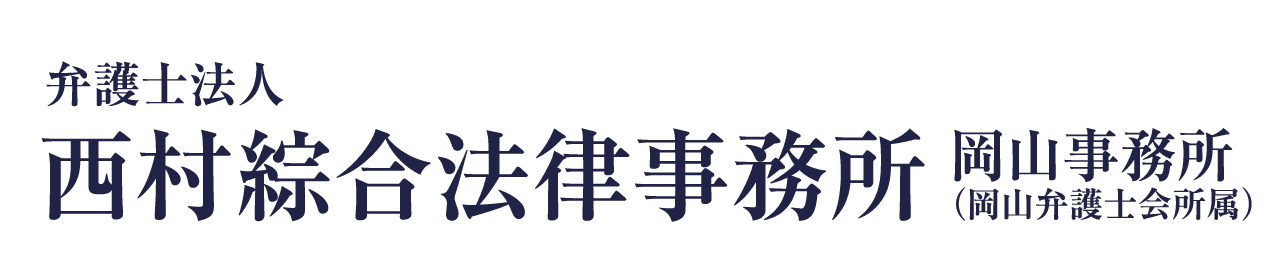交通事故の治療費打ち切りと症状固定について解説【弁護士監修】
目次
治療打ち切りは突然告げられます─
交通事故後まだ痛みが残っており、治療を継続したいと思っているにもかかわらず、保険会社から「交通事故から6ケ月以上経ったので、治療費を打ち切らせてほい。」と言われ、「今後の治療は、健康保険を使ってください」と言われたという被害者の方のご相談は、常に一定数あります。
場合によっては、治療打ち切りと同時に、「示談書を送るのでよければ署名捺印の上、返送してください」と言われる被害者の方も多く見えます。このような場合、どうすればよいのでしょうか。
結論としては、治療の必要性の検討という点に尽きます。弁護士が治療の必要性について検討をして、保険会社が治療の打ち切りを延期してもらったケースもあれば、そうはならなかったケースもあります。
治療の延長は、被害者本人でも可能?
治療の必要性を訴えて、治療の打ち切りを延期してもらうという交渉は被害者本人でも可能なのかという問い合わせも多くあります。
もちろん、不可能ということはないと思いますが、多くの場合、うまくいかないというのが、率直な感想です。
というのも、治療の必要性というものは、
①症状がどの程度の重さなのか
②打ち切りと言われるまでに、何か月間、治療費を保険会社が払ってきたのか
③主治医の見解はどうなのか
などの諸事情を総合的に判断される事柄であるからです。
事故の被害者の方が、専門知識や一定の経験も求められますので、被害者本人が効果的な交渉ができるかという点で、ハードルが高いと言わざるを得ないからです。
更に少し難しい話になってしまいますが、治療の打ち切りというのは、あくまでも保険会社が損害賠償として治療費を出す終期という意味に過ぎません。
ということは、単純に主治医の見解として、まだ治療の必要性があると言っても、同種類似の傷病で、多くの場合はすでに治療の打ち切り時点が到来するようなケースでは、被害者の側が「まだ治療費を出してくれ」といくら言っても、治療は打ち切られるケースもあります。
被害者の方としてはまだ痛みがあるのに、治療を打ち切ると言われ、詳しい事情がよくわからないまま、納得できないがために、保険会社に対して、何度も電話を掛けたりすると保険会社としては、過剰な要求を被害者がしている事例として、弁護士を入れてくるだけです。
保険会社から治療費を打ち切られた場合や症状固定した場合の対処方法
交通事故後、治療期間が長くなってくると、加害者の保険会社が治療費を
打ち切ってくることがあります。このような場合、治療を辞めずに症状固定するまで継続する必要があります。
また、医師に「症状固定した」と言われたときには、後遺障害等級認定を
受けるための準備を始めなければなりません。
今回は、保険会社から治療費を打ち切られた場合や症状固定した場合の正しい対処方法を、西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。
治療費を打ち切られた場合の対処方法
交通事故後、通院をするときには、加害者の保険会社が治療費を支払うので、被害者は病院に直接治療費を支払わないことが多いです。ところが、治療が長びいてくると、治療費を打ち切られることがあります。このようなとき、治療を辞めてはいけません。治療は、症状固定するまで継続する必要がります。途中で治療を辞めてしまったら、必要な治療を受けることもできませんし、入通院慰謝料も大きく減額されてしまいます。
症状固定とは、それ以上治療をしても、症状が改善しなくなった状態のことです。症状固定したかどうかは、医師が判断します。相手の保険会社は、支払を減らすために治療費を打ち切るので、もし打ち切りにあったら、自分の健康保険などを使って、通院を継続しましょう。
症状固定したときの対応方法
治療を継続していると、医師から症状固定を打診されることがあります。このとき、必要な治療や検査を終えているか、しっかり確認する必要があります。
たとえば、MRI検査は多くの疾患で非常に重要ですし、むちうちの場合にはジャクソンテストなどの神経学的検査が必要になることも多いです。高次脳機能障害の場合には、WMS-R(ウェクスラー記憶検査)や三宅式記銘力検査などの検査が必要です。
そして、後遺障害の認定を受けるために、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しますが、このとき、上記のようなさまざまな検査結果について、正確に記入してもらう必要があります。交通事故の後遺障害に慣れておられない医師の場合、時折、検査結果の記載をされないことがあるので、注意が必要です。
症状固定後に通院する意味と治療費を請求できるケース
一般に、交通事故でケガをした場合、治療は「症状固定」するまで継続します。
症状固定後は通院をしませんし、通院したとしても治療費が支払われません。
ただ、一定のケースでは、症状固定後の治療が意味を持つことがありますし、治療費の支払いが認められるケースもあります。
1.症状固定とは
交通事故で受傷したら、「症状固定」するまで治療を継続します。症状固定とは、それ以上治療を継続しても、症状が改善しなくなった状態です。症状固定するまでは、治療をしても意味がありますが、症状固定後は、治療を行う意味がなくなります。
そこで、症状固定時までは、加害者から、治療費や付添看護費用、入院雑費や通院交通費、休業損害などが支払われますが、症状固定後には、こういった費用の支払いは行われません。また、入通院慰謝料も、症状固定するまでの分が計算の基礎となり、症状固定後には入通院慰謝料が発生しなくなります。
そして、基本的に、症状固定したときに残っている症状が後遺障害となりますので、症状固定したら、後遺障害の等級認定を行う必要があります。後遺障害の認定を受けると、加害者に対し、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の失われた収入)を請求することができます。
2.症状固定後も、治療費を請求できるケース
ただし、症状固定しても、治療費を請求できるケースがあります。
たとえば、症状固定後、症状が悪化することを防止するために(安定した状態を維持するために)治療の継続が必要な場合です。また、症状固定をした後も、数度にわたって手術が必要になるケースなどもあります。
このように、症状固定後の治療が必要と認められる場合には、症状固定後の治療費も請求できますし、その際にかかった付添看護費用や通院交通費などの費用も請求できます。また、症状固定後も通院を継続していた場合、後遺障害認定を受ける際に、そのことが後遺障害を認める方向で考慮されることもあります。
以上より、症状固定したからといって、治療を辞めなければいけないとは限りません。
一刻も早く弁護士へご相談を
いずれにしても、治療の打ち切りの通知というのは、最終的な示談や、保険会社が弁護士を入れるかどうかなど、対応次第で今後の行く末が大きく変わるターニングポイントの一つと言えると思います。
言い方を変えると、治療の打ち切りの話が出た時点で、多くの場合、損害賠償の話となります。
多くの方は、よくわからない賠償金・補償金というお金の話が出てきますので、疑問に思うことがあれば、一度当事務所にご相談ください。なお、当事務所としては、事故直後からの相談をお勧めしております。
保険会社は交通事故被害者の味方なのか?
治療の打ち切りと関連して大切なことは、保険会社の担当者から後遺障害の等級認定手続きについての説明がきちんとなされているかという点です。
例えば、保険会社の担当者から「治療は打ち切らせていただきますが、症状が残っているようであれば後遺障害の等級に該当する場合もありますので、等級認定について検討してみてはいかがでしょうか。」という趣旨の説明はありましたでしょうか。
実は、治療の打ち切りで「保険会社の対応は終了です」と言われ、示談の話だけをされる被害者の方が一定数存在します。そして、残念なことに、後遺障害の話を一切聞かされないまま、示談をしてしまったという方も、少数ですがいらっしゃいます。
これでは、不幸にも症状が残ってしまい、本来であれば、後遺障害が認められ、後遺障害の分の補償を受けて当然の被害者の方が、後遺障害がない前提で示談をしてしまう結果になってしまいます。
交通事故で怪我をされ、治療の結果、治癒すれば問題ありませんが、治療期間が半年を超え、場合によっては年単位の治療が必要になったケースなどは、何らかの後遺障害が残ってしまうケースが多いです。
その場合は、損害賠償金の請求、示談よりも、まず先に、後遺障害の等級認定手続が行われるべきです。
適正な後遺障害等級の認定、そして賠償金の獲得を
被害者の方に後遺障害が残った場合、補償の肝となるべき部分は後遺障害の有無、等級認定の結果にあります。
これから一生、後遺障害と付き合っていく被害者の方に、後遺障害を前提とした補償がなされないことは、忌々しき事態であり、当事務所では、適正な後遺障害等級の獲得に注力しています。
後遺障害の認定手続きに関する疑問などがある場合も、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。