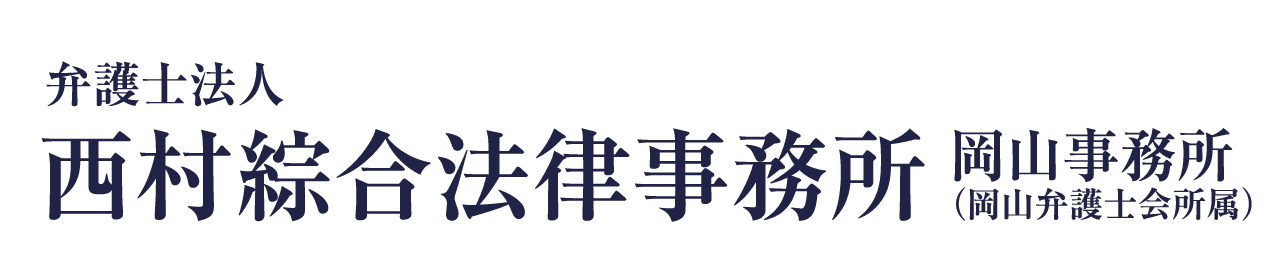バイクの交通事故の注意点と対処方法【弁護士執筆】
目次
バイク事故の注意点と対応方法
交通事故の中でも、バイク事故は被害者が重傷を負ったり死亡したりする割合も高いので、注意が必要です。
バイク事故でけがをすると、身体のさまざまな箇所に後遺障害が残ってしまうことも多いです。
今回は、バイク事故の特徴と注意点、対応方法について、西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。
1.バイク事故は、重傷率、死亡率が高い
バイク事故は、四輪車の事故と比べると、非常に重傷率や死亡率が高いです。
総務省の発表によると、平成28年度において、四輪車の事故の全体件数は412750件ですが、二輪車(原付のぞく)の事故は、31106件です。
その中で、死亡者数は、四輪車の場合1338人ですが、バイクの場合、460人です。
死亡率にすると、バイクの方が、5倍近くになっています。(自動車の死亡率は0.3%、バイクの死亡率は1.4%)また、重傷者数は、四輪車の場合10348人ですが、バイクの場合には4965人です。
重傷事故の率にすると、バイクが6倍となっています。(四輪車の場合2.5%、バイクの場合15%)。
このことから、バイクでは、いったん交通事故に遭うと、非常に重大な結果が発生する可能性が高いということがわかります。
2.バイク事故でケガをしたときの対処方法
バイク事故では、被害者が重傷を負うことが多いので、長期の入通院による治療が必要になることが多いです。この場合、症状固定するまで、確実に治療を継続することが重要です。
また、後遺障害が残った場合には、確実な方法で、より高い等級の後遺障害認定を受ける必要があります。
被害者の方が自分で対応すると、加害者の保険会社から入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を減額されたり、適切に後遺障害認定を受けられなかったりすることが多いので、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要です。
3.バイク事故で被害者が死亡したときの対処方法
バイク事故では、残念ながら、被害者が死亡してしまわれることも多いです。
この場合、加害者の保険会社からは、被害者に大きな過失割合を割り当てられたり、慰謝料を減額されたりするので、遺族が納得できないと感じることがよくあります。
そこで、やはり、法律の専門家である弁護士が示談交渉に対応する必要があります。
バイク事故で後遺障害が残った場合はどうすればいい?
バイク事故では、被害者が重傷を負うことが多いので、後遺障害が残ってしまわれる方がたくさんおられます。
バイク事故の後遺障害には、どのようなものがあるのか
実際に後遺障害が残ったとき、どのような手続きをとれば良いのか
理解しておきましょう。
今回は、バイク事故で後遺障害が残った場合の対処方法について、西村綜合法律事務所の弁護士が解説します。
1.バイク事故でよくある後遺障害
バイク事故は、四輪車の事故と比べて、被害者が重傷を負うことが多いです。バイク事故の後遺障害には、以下のようなものがあります。
●高次脳機能障害
脳に損傷を受けたときに発症する障害です。
認知機能に障害が発生するために、日常で必要な動作もできなくなることがあります。
●胸腹部臓器の障害
呼吸器や心臓、胃腸や腎臓、生殖器など、各種の身体の器官に障害が残ります。
●手や足の後遺障害
腕や脚の骨折、手指足指の喪失や機能障害などです。
●目や鼻、口などの後遺障害
目が見えなくなったり、鼻が欠けたり、ものが噛めない、言葉を話せないなどの障害が残ります。
● 外貌醜状
顔面にけがをすると、傷跡が残ってしまいます。
このように、後遺障害が残った場合には、後遺障害の等級認定を受けなければなりません。認定を受けないと、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることが難しくなってしまうからです。
2.後遺障害認定を受ける方法
後遺障害の認定を受ける方法としては、事前認定と被害者請求という2種類の方法があります。
被害者の方が自分で示談交渉をしているときには、相手の任意保険会社に任せる「事前認定」を利用されることが多いのですが、これでは加害者の保険会社に任せきりにしてしまうので、不安があります。
より確実に認定を受けたいなら、被害者自身が認定請求の手続をする「被害者請求」を利用する必要があります。ただ、被害者請求をするにしても、手続きの内容や流れ、専門のノウハウなどが必要ですし、最低限の医学的知識も必要です。
確実に認定を受けるためには、交通事故問題に強いによるサポートが重要となってきます。
西村綜合法律事務所は後遺障害等級認定を非常に得意としている事務所であり、これまで高い実績を誇っています。治療中の方へのアドバイスも可能ですので、バイク事故で後遺障害が残った方や残りそうな方は、お早めにご相談下さい。