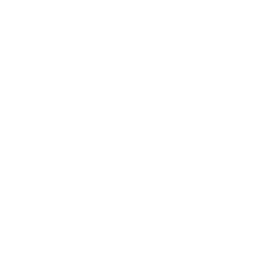人事労務・企業法務のトラブルは弁護士へ!労働組合・パワハラ・解雇など対処法8パターンを徹底解説
未払い残業代請求
未払残業代が発生する原因
未払残業代が発生する原因には様々なものが考えられますが、大きく分けると、従業員の労働時間の管理が不十分であった場合と、残業代に関する法制度についての理解が不十分であった場合の2パターンが多いと考えられます。
未払残業代を請求されてしまったら
労働者から未払残業代を請求された場合、以下の点をチェックする必要があります。
①従業員が時間外労働を行っているか
タイムカードや出勤簿などの記録を確認し、従業員の主張のとおり時間外労働が行われていたのかを確認する必要があります。
会社が残業を禁止していたり、残業許可制を採用していたにもかかわらず許可なしで残業が行われているような場合は、タイムカードや出勤簿上就業が確認されたとしても、労働時間と評価されない可能性があります。
②従業員に残業代が生じているか
従業員に法定労働時間を超える労働時間が確認された場合でも、従業員が、管理監督者などに該当し、残業代を支払う必要がない業務形態になっていないかを確認する必要があります。
③従業員に残業代が生じていても既に支払っていないか
従業員に残業代を支払う義務が生じていたとしても、固定残業代制度などの適用により、既に適正に支払われているといえないかを確認する必要があります。
④未払残業代請求に消滅時効が適用されないか
従業員に支払われていない残業代が存在した場合でも、消滅時効が適用されるときは、企業は残業代の支払い義務を負いません。そのため、消滅時効の適用が認められるかを確認する必要があります。
なお、賃金請求権の消滅時効期間については、2020年4月1日より3年に延長されています。
未払残業代の発生を未然に防止する方法
上記のとおり、未払残業代が発生する大きな原因としては、労働者の労働時間の管理が不十分であった場合、あるいは、残業代に関する法制度についての理解が不十分であった場合の2パターンが多いと考えられます。
①労働者の労働時間の管理が不十分であった場合
無駄な未払残業代の発生を防ぐには、適正に従業員の労働時間を管理し、いわゆるダラダラ残業をなくす必要があります。
企業内において、業務の効率性を図ると共に、従業員の間においても残業はよくないものだという認識を持ってもらうことで、必要のない時間外労働を削減することが重要になります。
また、企業が残業を禁止する、あるいは残業許可制を採用することで、従業員から不意に残業代の支払いを求められるという事態を防止することができます。
②残業代に関する法制度についての理解が不十分であった場合
また、未払残業代の発生を防止するためには、残業代に関する法制度を正確に理解し、法律を適正に運用する必要があります。
例えば、管理監督者に該当する労働者に対しては、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う必要はありませんが、そもそも、裁判例上、管理監督者に当たるかは、以下の点を考慮して、客観的に判断されるべきとされています。
- 労務管理上の使用者との一体性
- 労働時間管理を受けていないこと
- 基本給や手当面でその地位にふさわしい処遇を受けていること
このような制度に関する理解が不十分であると、思いがけず残業代を支払わなくてはならなくなる可能性があるため、要件をきちんと満たしているか慎重に検討する必要があります。
また、管理監督者に該当する労働者であっても、企業は、深夜労働に対する割増賃金については支払義務を負っています。
「管理監督者に該当する従業員に対しては、一切の割増賃金は支払わなくてよい」と誤解した企業も少なくないため、残業代に関する法制度を正確に理解しなければなりません。
問題社員対応
問題社員の類型
問題社員をタイプ別に見てみると大きく以下のように分類することができます。
①能力欠如型
従業員の能力が欠如しており、会社が求めるクオリティを労働者が発揮できていないパターンです。
②勤怠不良型
従業員が理由もなく、遅刻や早退、欠勤を繰り返すパターンです。
③メンタル型
精神疾患になって勤務することができない従業員のパターンです。
④セクハラ・パワハラ型
従業員が他の従業員に対して、セクハラ・パワハラを行ってしまうパターンです。
⑤私生活上の問題行動型
企業の業務外の私生活において、従業員に問題が存在するパターンです。
絶対にやってはいけない対応
たとえ、上記のような問題社員であっても、十分な検討を行う前に従業員を解雇すべきではありません。
後述のとおり、企業が従業員を解雇することができる場合は、制限的に考えられており、適法に従業員を解雇するためのハードルは企業が考えているよりも高い場合があります。
仮に解雇が無効と判断される場合、従業員は、解雇相当期間中の賃金相当額の支払い(バックペイ)を請求することが可能とされ、また、違法な解雇により精神的な苦痛を被ったとして損害賠償請求を行うことも可能とされています。そのため、解雇が無効と判断される場合、企業に大きな負担が生じてしまいます。
従業員に問題がある場合でも、弁護士に意見を求めるなど慎重に対応すべきであり、早計に解雇手続を実施することは避けるべきです。
類型別問題社員への適切な対応方法
問題社員のタイプ別の対応方法は以下のとおりです。
①能力欠如型
能力欠如型の社員の場合、会社が求める労務のクオリティと従業員自身の労務のクオリティの認識に解離が生じている場合が多いです。
そして、能力不足だけを理由に解雇するには相応の理由が必要と考えられています。そのため、従業員に求める労務のクオリティの水準を明確に伝え、さらに、従業員の労務のクオリティがこれに達しない場合は、そのことを従業員に伝え、改善を期することになります。
②勤怠不良型
遅刻、早退、欠勤なく労務を提供するというのは、労働契約における労働者の基本的な義務内容であり一種の社会常識といえますが、遅刻、早退、欠勤が多いというだけで直ちに解雇を行うことは困難です。そのため、遅刻、早退、欠勤が多いようであれば、まずは注意を行い、それでも改善が見られない場合は、厳重注意、あるいは懲戒処分を実施することになります。
重要なことは、企業が繰り返し注意しても改善が見られなかったということを客観的証拠として残すことであり、注意や厳重注意を行ったに過ぎない場合でも報告書などで内容をまとめておくことが必要です。
③メンタル型
従業員が精神疾患になって勤務することができない場合、多くの企業では休職制度を適用し、休職させることになります。そして、休職期間満了時に休職事由が消滅していない場合は、就業規則の規定に従い解雇あるいは退職という流れになります。
④セクハラ・パワハラ型
セクハラ・パワハラを放置してしまうと、被害者となった従業員だけではなく、他の従業員にも悪影響を及ぼす可能性が高いといえます。そのため、後述のとおり、事実関係を確認し、セクハラ・パワハラが認められた場合は注意、処分を行い、再発防止策を実施するという手順を踏む必要があります。
⑤私生活上の問題行動型
従業員の私生活上の問題行動が、企業秩序の維持に悪影響を及ぼす場合や労働契約の義務違反を生じさせる場合、そのような問題行動は、懲戒処分や普通解雇の理由となる可能性があります。
もっとも、従業員の私生活上の問題行動といってもその内容は多種多様であり、企業の信用がどの程度失墜したか、私生活上の行動が企業の業務内容とどのように関係するか、従業員の企業での地位や業務内容、結果の重大性といった観点を考慮して処分内容を定めることになります。
セクハラ・パワハラ問題
セクハラ問題が発生した際の対応方法
セクハラ問題が発生した際の対応方法としては、事実関係を確認し、セクハラが認められた場合は注意・処分を行い、同じ被害が生じないように再発防止を実施するという手順を踏む必要があります。
①事実関係の確認
被害を主張している従業員から話を聞き、その後に加害行為を行ったとされる人物の話を聞くことになります。もっとも、いずれの当事者からも詳細に話を聞くことがポイントになります。
②注意、処分
事実関係の確認の結果、セクハラが認められた場合は注意、処分を行うことになります。ただし、セクハラ行為を行った従業員に対する処分の内容が重すぎる場合、従業員から処分の無効を主張される可能性が存在する一方、処分の内容が軽すぎる場合でも、再発防止には繋がらず、被害者も納得しないという状況が生じてしまいます。
そのため、確認された事実の内容に応じて重すぎず軽すぎない適正な処分を行うことが重要になります。
処分の内容に関しては、人事院が国家公務員の非違行為に関し、「懲戒処分の指針について」を公表しており、参考になります。
③再発防止
注意、処分の後は、同じ被害が生じないように再発防止を実施することになります。
セクハラが生じないように事前に防止する方法については、後述のような対応策が存在するところですが、既に発生していしまったセクハラ問題に関しては、「なぜ本件ではそのような問題が生じてしまったのか」という点を炙り出し、その原因に焦点を当てて対応する必要があります。
パワハラ問題が発生した際の対応方法
パワハラ問題が発生した際の対応方法も基本的には、セクハラ問題が発生した際と同じように、①事実関係の確認、②注意、処分、③再発防止という手順を踏む必要があります。
もっとも、パワハラの場合は上司が部下を叱責する場合に問題になることが多いのですが、セクハラの場合と異なり、上司の叱責も業務上遂行の一環として行われる点に特色があります。そのため、被害を申告している従業員側の事情も考慮して、適正な範囲の叱責かどうかを検討する必要があり、微妙な判断を迫られる場合も少なくありません。
ハラスメント問題を発生させないためにするべき対策
企業において、どのようにハラスメントを防止していくかに関しては、厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」というウェブページにおいて、ポイントが示されており、参考になります。
①ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
ハラスメントの内容を具体的に説明し、ハラスメントを行ってはならないという企業の方針を示すことで、労働者に周知・啓発を行うことが可能になります。
②行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
ハラスメントを行った者は厳正に対処する旨の方針を明確に示し、実際にハラスメントが起きた際にも厳正に対処することで、ハラスメントの被害を防止することに繋がります。
③相談窓口の設置
ハラスメント防止に関しては、相談窓口を設置し、その存在を周知・啓発することも重要です。ハラスメント被害が生じた場合に被害者が相談できる環境を整備することで、結果として、ハラスメントを防止する機能を発揮することになります。
④ハラスメント防止に関する研修
研修の実施もハラスメント防止には有用です。従業員の職務内容や就業環境、職階ごとにハラスメントの加害者になりやすいか、被害者になりやすいかといった点が異なります。そのため、ハラスメント防止に関する研修も、このような観点から従業員をグループ化し実施することが有効と考えられています。
労働組合・団体交渉
労働組合対策・団体交渉とは
労働者が労働組合を組織し、労働条件などについて協議を求める場合があります。このような労働者の組織を労働組合といいます。
労働組合は企業内部で組織されることもあれば、企業外部で組織されることもあります。特に中小企業労働者から構成される企業外部の労働組合をユニオンと呼びます。
団体交渉を申し立てられた際に取るべき対応
労働組合が団体交渉を申し入れる場合は、交渉申入書や要求書といった書類を企業に送付することになりますが、団体交渉を申し立てられた企業としては、まず、誰がどの労働組合に加入したのか、何の事項について交渉が申し立てられたのかについて確認する必要があります。
絶対にやってはいけない対応
労働組合は、一般的に弱い立場にある労働者が、企業を始めとした使用者と対等な立場にたって、労働条件を交渉することができるように認められた組織です。そのため、労働組合が団体交渉を行う上で不当な妨げとなるような行為は、不当労働行為として法律上禁止されています。
労働組合から団体交渉を申し立てられた場合、使用者は不当労働行為を行ってはなりません。具体的には以下の行為が禁じられています。
①団交拒否
企業は、団体交渉を行うことを正当な理由がなく拒むことができないとされており、正当な理由のない団交拒否は不当労働行為として禁止されています。また、単に企業は交渉の席に就けばよいという訳ではなく、労働組合と誠実に交渉を行わなくてはならないという誠実団交義務が課されています。
そのため、団体交渉においては、必ずしも労働組合の要望を飲む必要はありませんが、企業は自身の主張の根拠を具体的に説明し、その資料を提示するなど誠意ある対応を採ることが求められます。
②労働組合の結成、加入、組合活動を理由とする不利益取扱い
企業は、従業員が労働組合の組合員であること、労働組合に加入したこと、結成しようとしたことをもって不利益な扱いをしてはいけないとされており、不当労働行為として禁止されています。また、労働者が労働委員会に救済の申し立てをしたことを理由として不利益な扱いをしてはいけないともされており、これも不当労働行為として禁止されています。
③支配介入
労働組合の性質に照らせば、労働組合は使用者である企業から独立していることが求められます。そのため、企業が労働者に組合脱退の働きかけを行う、組合の幹部の解雇や配転を行うといった行為により、労働組合の運営に支配介入する行為も不当労働行為として禁止されています。
④経費援助
労働組合の独立性の観点から、使用者が労働組合を経済的に支配介入する経費援助行為も禁止されています。そのため、労働組合法7条3号但書きで例外的に許容されている場合を除いて、経費援助行為は不当労働行為として禁止されています。
⑤黄犬契約
労働組合から団体交渉を申立てられた時点において、問題になることはあまりありませんが、労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを条件に雇用する黄犬契約についても、不当労働行為として禁止されています。
退職勧奨
退職勧奨とは
退職勧奨とは、企業が従業員に自主的な退職を促すことをいいます。企業と従業員間で協議を行い、合意により労働関係を解消する方法です。
後述のとおり、企業においては、労働者に退職してもらう必要が生じた場合であっても、簡単には解雇することはできないとされています。そのため、企業において、労働者に退職してもらう必要が生じた場合、まず退職勧奨を行い、当事者間の話し合いを行うことが多いです。
認められない退職勧奨の方法
退職勧奨はあくまでも、労働者との意思を尊重する態様で行うことが必要となります。そのため、事実上、労働者に退職を強要する形になる退職勧奨を行うことは認められません。
そして、企業が労働者の人格的利益を侵害する態様で退職勧奨がなされた場合は、不法行為に該当し、労働者から損害賠償請求がなされる可能性が存在します。
また、違法な退職勧奨が存在する場合は、労働者が辞職した場合であっても、その意思表示に錯誤、詐欺、強迫があったことを理由に辞職が無効であると主張される可能性が存在します。
適切な退職勧奨の方法
適切に退職勧奨を行うには、労働者の人格的利益を侵害しないよう様々な点を配慮して行う必要がありますが、特に以下の点について注意する必要があります。
- 長時間あるいは多数回にわたり退職勧奨を行うことは避けること
- 労働者の名誉を毀損するような侮辱的な発言は避けること
- 嫌がらせ目的で労働者の業務を変更したり仕事を与えないといった行為は行わないこと
解雇問題・整理解雇
解雇の種類と解雇要件
解雇とは、企業が一方的に従業員との労働関係を解消することです。
解雇の種類としては、主に、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇が存在し、それぞれの解雇要件は以下のとおりです。
①普通解雇
普通解雇は、従業員が労働契約において定められた義務を履行しない場合に認められる解雇を言います。
もっとも、従業員にとって、雇用関係は生活の基盤であり、簡単に雇用関係を解消できるとすると、労働者の不利益があまりに大きくなってしまいます。
そのため、労働契約法第16条においては、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする、と規定されており、普通解雇を行うには、客観的合理性と、社会的相当性といった要件を満たす必要があります。
②整理解雇
整理解雇とは、余剰となった人員を整理するため従業員を解雇する場合の解雇のことをいいます。
整理解雇は、企業の経営状況が悪化した場合にやむを得ずに行われる場合がありますが、そのような場合であっても、裁判例において、以下の要件を満たす必要があるとされています。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力の実施
- 人選の合理性
- 手続の妥当性
③懲戒解雇
懲戒解雇は、従業員に非違行為が認められる場合に、制裁として行われる解雇処分のことを言います。
会社の行いうる最も重い懲戒処分となります。
懲戒解雇は、懲戒処分の一種であることから、就業規則上、懲戒解雇事由が規定され、従業員の非違行為がこれに該当する必要があります。また、懲戒処分として解雇を行うことになるため、その処分を行うことに関し、客観的合理性と、社会的相当性といった要件を満たす必要があります。
解雇は簡単にはできない
従業員にとって雇用関係は生活の基盤であり、その生活を保障する必要があります。また、日本では定年雇用制が慣行として根付いてきたという事情も存在します。
そのため、簡単には労働者を解雇することはできないという事情が存在し、企業が解雇手続を行う際には慎重に判断が求められています。
不当な解雇だと言われた際の対応方法
解雇という手続は、労働者の生活に直接の悪影響を及ぼすものであり、労働者の一生を左右する可能性がある手続です。また、仮に解雇が無効と判断される場合、従業員は、解雇相当期間中の賃金相当額の支払い(バックペイ)を請求することが可能とされ、違法な解雇により精神的な苦痛を被ったとして損害賠償請求を行うことも可能とされています。
そのため、従業員から不当な解雇だと言われた場合、法的な紛争に発展する可能性が極めて高い状況にあると考えられます。企業はとしては、その時点で、裁判に備え、改めて、解雇理由に関する主張を整理し、解雇理由を証明する証拠をきちんと保存することが求められます。
労働審判
労働審判とは
労働審判は、企業と労働者間の労働関係のトラブルを迅速かつ適正に解決するために運用が開始された裁判手続です。
従前、企業と労働者間の労働関係のトラブルを終局的に解決するには、訴訟を提起する必要がありましたが、訴訟の場合、判決が出されるまでに時間がかかり、負担が重いことが指摘されていました。
これに対して、労働審判は以下のような特徴をもっており、労働関係のトラブルを迅速かつ適正に解決することが可能になっています。
- 労働審判は、裁判官1名、労働審判員2名の3名で審理が行われます。そして、労働審判員のうち、1名は労働者側の労働審判員が選任され、もう1名は使用者側の労働審判員が選任される形になっています。そのため、労使双方に配慮した審理運営を期待することが可能とされています。
- 労働審判は、原則として3回以内の期日で審理が終結されます。また、労使双方が、やむを得ない場合を除いて、2回目の期日が終了するまでに、主張と証拠書類の提出を行わなければならないとされています。
- 労働審判においては、訴訟以上に口頭でのやり取りが実施されます。そのため、争いになっている事実関係については、十分確認のうえ、口頭でも説明することができるようにしておくことが重要です。
- 労働審判は、迅速で簡易な手続であるため、手続に要する費用も安くなっています。例えば、必要となる収入印紙の額は訴訟に比べて半額程度で済みます。
労働審判の流れ
労働審判の申立てから審判までの主な流れは以下のとおりです。
- 労働審判手続を利用しようとする申立人が、地方裁判所に申立書等の必要書類を提出します。
- 裁判所は、申立てがなされた日から40日以内の日に第1回の期日を指定し、当事者双方を呼び出します。相手方は、裁判所から期日呼出状、申立書の写し、証拠などの資料一式が送付されますので、指定された期限までに、答弁書や証拠を提出して反論を行うことになります。
- 裁判所が指定した日程において、期日が開催され、審理が行われます。労働審判手続では、原則3回まで審理の期日が開催されますが、稀に4回目以降の審理の期日が開催されることもあります。労働審判の期日においては、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聞き、争点を整理し、必要に応じて申立人や関係者から直接事情を聴くことになります。その期日の中で、話合いによる解決の見込みがあれば、裁判所が調停案を提示するなどして、調停での解決を試みることになります。
- 当事者間において、話合いによる解決が行われない場合、労働審判委員会が、審理の結果を踏まえて、紛争の解決内容を判断し、労働審判を下すことになります。
- 労働審判の内容に納得ができない場合、異議申立てを行うことが可能であり、当事者のいずれかが異議申立てを行った場合、審判は失効し、手続が通常訴訟に移行し、訴訟手続によって、判決が下されることになります。
就業規則
就業規則を変更する際の注意点
就業規則は、企業と労働者間の労働条件や、職場規律について定めた規則のことをいいます。
企業は就業規則を用いて多数の労働者との労働契約の内容を規律していますが、経営状況の変化や法改正を理由に就業規則を変更しなければならない場合があります。その際、以下の点に注意する必要があります。
①適正な手続を踏むこと
就業規則を変更する場合は、作成時と同じような手続を実施する必要があり、具体的には以下のような手続を踏む必要があります。
- 変更後の就業規則を、以下のいずれかの方法で労働者に周知する
- 常時作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
- 書面で交付する
- 磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
- 労働者の過半数を代表する者から就業規則の変更について意見を聞く
- 必要書類と共に労働基準監督署に届け出る
②不利益変更の場合、就業規則の変更内容が合理的であること
就業規則の内容により、従業員の労働条件が不利になる場合、労働者の同意が必要になります。もっとも、就業規則変更後の労働条件の内容が、以下の要件に鑑み、合理的と認められる場合には、労働者の同意がなくても、就業規則の内容を変更することができます。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 規則を変更する必要性
- 規則の変更後の相当性
- 労働者との交渉の内容
そのため、就業規則を従業員にとって不利益に変更する場合には、これらの要素に照らして、その変更が許容されるかを検討する必要があります。
就業規則見直しのポイント
企業の規模、業種が様々であるように、企業と労働者間の適正な労働関係も企業ごとに様々です。
そのため、企業で使用している就業規則が、単なるひな形ではなく、実情に沿ったものとなっているかという点に着目して、見直しを行う必要があります。
また、労働に関する法制度は、法改正が行われることが多い分野です。そのため、法改正が行われる度に、就業規則の内容が法令に沿った内容になっているのかを確認する必要があります。
よくある就業規則の間違い
よくある就業規則の間違いは以下のようなものがあります。
例えば、有期労働者、パートタイマー、嘱託社員など、正社員と異なる取扱いを行う労働者がいる場合は、それらの異なる種類の労働者ごとに就業規則を作成する必要があります。
仮に、労働者の種類ごとに就業規則を作成していない場合は、正社員用の就業規則が適用されることになりますので、パートタイマーの従業員に退職金を支払う必要が生じるなど、思わぬ事態に陥る可能性があります。
また、固定残業代制度に関する記載が不十分な場合も多く見受けられます。
固定残業代制度の有効要件については争いがあるところですが、一般的には、賃金の支払いに当たり通常の労働時間分の賃金部分と割増賃金部分を区別することができること(明確区分性の要件と呼ぶことがあります)が求められます。
この点、「月額の賃金40万円のうち、10万円が40時間分の残業代である」という記載や「月額の賃金40万円のうち、10万円が固定残業代である」という記載が存在すれば、通常の労働時間分の賃金部分と割増賃金部分を区別することが可能と考えられています。
他方、「月額の賃金40万円のうち、10時間分の残業代が含まれている」という記載しか存在しない場合は、通常の労働時間分の賃金部分と割増賃金部分を区別することはできず、明確区分性の要件を満たさないと解される可能性が高いとされており、注意を要します。
人事労務トラブルは弁護士に相談を
本格的な労使紛争になってからでは遅い
労働者とのトラブルが、本格的な労使紛争に発展した場合、自身の生活が懸かっていることを理由に、徹底的に争われることが多く、紛争が複雑化、長期化する傾向があります。場合によっては、労働組合や労働基準監督署に関する対応も必要になるため、紛争の対応それ自体が企業の負担となってしまいます。
そのため、人事労務に関しては、就業規則の改善や社内規律の徹底などを通して、予防法務を実施し、無用な労使紛争を生じさせないということが重要になります。
人事労務トラブルは幅広いため、弁護士に一任するのがおすすめ
人事労務に関するトラブルは、上記のように様々な類型が存在します。また、解雇訴訟など、労働問題は、個々の事案ごとに応じた具体的な判断が求められるという特徴があります。
そのため、労働問題に詳しい弁護士に一任することで、裁判例や裁判実務的な感覚に沿った対応を行うことが可能になります。
訴訟を見据えた事前の対策が可能
また、弁護士に人事労務に関するトラブルを相談することで、訴訟を見据えた事前の対策を行うことが可能になります。
当事務所に人事労務問題を相談いただくメリット
当事務所においては、人事労働問題、労働紛争、労働訴訟に力を入れており、詳細な知識と経験を有した弁護士が在籍しています。
これらの人事労務問題に関するご相談は是非ご相談ください。