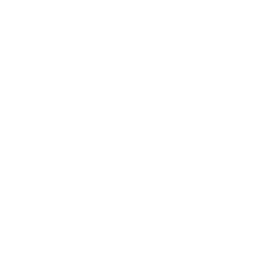労働訴訟を起こされた!類型別の対応8選を弁護士が解説
労働者から訴訟を起こされることは、企業としては絶対に避けるべき事態です。もっとも、どれほど適切に労務管理を行っていたとしても、労働災害など避けようがない事情が発端で訴訟を提起されることもありえます。
そこで、本記事では、万が一、労働者から訴訟を起こされた場合に適切に対応するために、企業がとるべき対応を紹介します。
労働訴訟に関する基礎知識
まずは、労働訴訟に関する基礎知識を確認しましょう。
労働訴訟とは
労働訴訟という言葉は頻繁に使われておりますが、労働訴訟という特別な訴訟類型があるわけではなく、また、司法制度において明確な定義づけがされている言葉でもありません。一般的には、使用者と労働者との間の労働契約を前提として起こる様々な紛争を総称して、「労働訴訟」と呼称されていることが多いと思われます。
労働訴訟に発展しやすい事例
労働訴訟に発展しやすい類型とは、言い換えると、使用者と労働者との間の紛争となりやすい事例です。以下、使用者と労働者個人の間でよく見られるケースを紹介しますが、使用者と労働組合とで紛争が起こる場合ももちろんあります。
ハラスメント問題
近年急速に社会問題化し、労働関係の新たな違法行為の類型となったものにセクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントがあります¹。それぞれ、セクハラ、パワハラと略称され、男女雇用機会均等法や労働施策推進法の改正等、立法による手当てもされていますが、ハラスメント問題は後を絶ちません。
ハラスメント問題は、被害者から加害者への不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求事件、被害者から企業への労働契約上の安全配慮義務違反(労働契約法5条)に基づく損害賠償請求事件として事件化されます。ハラスメントに関する事件の多くは、ハラスメント行為の有無について事実認定の問題、損害額の多寡について法的評価の問題が争点となります。
残業代請求
残業代、すなわち未払賃金につき、労働契約上の賃金支払請求事件として事件化されます。
労働者側の主張として多いのは、サービス残業をさせられていた、時間外労働に対する割増賃金が支払われていない、といったものです。この場合、労働者の実労働時間をどのように事実認定できるのかが、一つの争点となります。また、近年、固定残業代制度に関して最高裁判所の判断²が下されたことから、固定残業代として支払われていた手当が、本来支払われるべき時間外労働に対する割増賃金に不足しているという主張も少なくありません。
これに対して、使用者としては、実際にそのような残業はしていなかったこと、当該労働者は管理監督者(労働基準法41条2号)に当たるため時間外労働に対する割増賃金は発生しないこと等を主張していくこととなります。
給与の設定
懲戒処分の一つ、あるいは、人事異動上の措置としての「降格」が行われ、それに伴って給与の引き下げが行われる場合も紛争が生じやすい一つの類型です。
労働者は、従前の給与で労務を提供する地位があるとして、労働契約上の地位確認を求めることとなります。そのなかで、懲戒処分や人事権の行使が無効であるという主張を展開していくこととなります。
無効の理由として最も多いのは、懲戒権や人事権の濫用です。労働者と使用者は、それぞれ濫用があった、あるいはなかったという主張を交わすこととなります。
労働訴訟の種類と対応時のポイント
次に、労働訴訟の種類と、それぞれの類型に応じた対応のポイントを説明します。
民事訴訟
一つ目の類型は、民事訴訟です。
民事訴訟の概要
民事訴訟法の下、通常の民事訴訟手続が行われ、主張整理、証拠調べの順に審理が進行します。労働訴訟であることを理由に、他の事件類型と異なるところはありません。
対応時のポイント
民事訴訟では、当事者の権利を実現する手続とされており、主要事実やその認定のための証拠の提出を当事者の責任で行うという弁論主義が採用されています。
そのため、いかに説得的な主張を展開できるか、また、その主張を価値の高い証拠で支えることができるかという点が肝要です。
労働審判
次に、労働審判です。
労働審判制度の概要
第1に、地方裁判所において、裁判官1名と労働関係の専門的な知識経験を有する者2名(労使それぞれから1名ずつ)によって構成される合議体(労働審判委員会)が紛争処理を行うことです。
第2に、紛争が労働者の生活をかけた紛争であることから、原則として「3回以内の期日において、審理を終結させなければならない」(労働審判法15条2項)として、紛争の迅速で集中的な解決を図ることにあります。
第3に、権利紛争に関する審判手続の中に、調停を包み込んでいることです。
第4に、調停によって紛争を解決できない時に、権利関係を踏まえつつ、事案の実情に即した解決を行うための審判を下す(同1条)ことにあります。審判では、権利関係を確認したり、金銭の支払等の財産上の給付を命じたりすることができ、また、その他紛争の解決のために相当と認める事項を定めることができます(同20条2項)。
第5に、訴訟手続と接続していることです。当事者から異議の申立てがあれば、労働審判は失効し(同21条3項)、労働審判の申立ての時に遡って訴えの提起があったものとみなされます(同22条1項)³。
なお、労働審判手続は、使用者と個人労働者との間の労働紛争を解決する制度であり、使用者と労働組合との間の団体的労働紛争はその対象外となります。後者は、労働委員会によって解決されることとなります。
対応時のポイント
原則として、期日が3回以内で終了するという仕組みは、使用者にとっては非常に大きな負担となります。さらに、労働審判の第1回期日は、原則として申立て日から40日以内に指定されます(労働審判規則13条)。この期日を、被申立人の事情で変更することは原則できませんし、また、民事訴訟のように擬制陳述の制度もありません。労働審判は、大部分が労働者の申立てによって開始しており、使用者としては迅速な対応が求められます。
また、こうした期日回数の規制から、労働審判の場には、口頭説明が可能な程度に事情を十分に把握している担当者が出席することが必須です。さらに、調停を内包しているという点からも、当事者同士が常に同意を形成することができるように、人事権の決裁官が出席する、あるいは少なくとも常に連絡が取れるように待機していただくことが望ましいでしょう。
仮処分
続いて、仮処分です。
仮処分の概要
仮処分は、民事保全法における概念です。保全とは、通常訴訟における権利の実現を保全するために、簡易迅速な審理によって、裁判所が一定の仮の措置を取る暫定的・付随的な訴訟手続です。解雇された労働者が、従業員たる地位を仮に定める(地位保全仮処分)とともに、賃金の仮払いを命じる仮処分(賃金仮払い仮処分)を申し立てるのが典型例です⁴。
仮の地位を定める仮処分においては、口頭弁論または審尋が必要とされています(民事保全法23条4項)。審尋期日においては、原則として当事者のみが審尋の対象となります。当事者以外の者が陳述をできる場合もありますが、その場合には陳述書を提出することが多いです。
対応時のポイント
申立人が被保全権利、保全の必要性について疎明をした場合、保全命令が発令されることとなります。
保全命令が下されると、保全債権者(申立人)は、当該命令に基づいて保全執行をすることができます。保全執行に対しては異議申立てをすることができ、執行段階で改めて権利を主張することとなります。
労働訴訟の際の具体的な流れと企業がとるべき対応
最後に、労働訴訟のうち、民事訴訟に限定して、具体的な手続きの流れを説明します。
訴状が届く
まず、訴えが提起されると、相手方となる使用者のもとへ、訴状が届きます。これを見て、どのような紛争かを把握しましょう。
答弁書の裁判所への提出
次に、答弁書を提出します。
民事訴訟であれば、擬制陳述をして、十分に反論を練る時間を設けることが可能です。ただ、擬制陳述をする旨の答弁書を提出しないと原告の主張を認めたこととなってしまいますので、忘れずに提出しましょう。
口頭弁論期日
口頭弁論期日では、双方が証拠をもとに主張を展開し、一方の主張に対して反論をしていきます。
書面でやり取りをしていく中で、争点が明確になり、双方の主張が整理されていくこととなります。その段階で証拠調べを行います。ここでいう証拠調べとは、証人尋問です。通常、証人尋問は、訴訟手続の終盤に行われます。
判決
最終的に、裁判所が判決を下します。
なお、判決までに、少なくとも2回程度は、裁判所から和解の勧試があります。裁判所の和解案や当該時点での心証を聞いて、和解をするか否か、するとして条件をどうするかを検討することとなります。
労働訴訟問題は弁護士にご相談ください
以上、労働訴訟について説明しました。
訴訟というと、勝敗が明確になるというイメージを持たれる方も多いかと思いますが、何をもって勝ちとするかはまさにケースバイケースといえ、様々な事情を考慮して総合的な判断をする必要があり、その中で弁護士の知識と経験に基づく専門的判断が必要なケースもあるかと思います。
労働訴訟問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
- ¹ 菅野和夫『労働法(第十二版)』226頁(2019年,弘文堂)
- ² 日本ケミカル事件(最判H30.7.19 労判1186号5頁)
- ³ 前掲¹菅野1147~1149頁
- ⁴ 前掲¹菅野1172頁